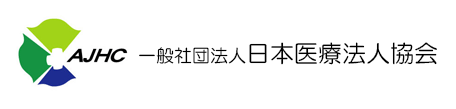日本医療法人協会ニュース 2025年3月号

■巻頭言
日本医療法人協会 常務理事/社会医療法人社団慈生会 等潤病院 理事長・院長 伊藤 雅史
■特別座談会
林 修一郎・厚生労働省保険局医療課長を迎えて 2026年度診療報酬改定を展望する
全国一律の診療報酬制度で地域の課題とどう向き合うか 先入観を持たずに議論を
■特別レポート
福祉医療機構「経営状況」レポート
病院の経営状況悪化が浮き彫り 収益増が支出に追いつかず
●NEWS DIGEST医療界の最新動向
●独立行政法人福祉医療機構貸付利率表
●編集後記
日本医療法人協会 常務理事
社会医療法人社団慈生会 等潤病院 理事長・院長
伊藤 雅史「医療DX令和ビジョン2030」厚生労働省推進チーム第6回会合にて「病院の情報システムの刷新に係る方向性(以下、方向性)」が示された。
これまで国が進めてきた医療DXは、マイナ保険証・電子処方箋の普及や行政の効率化を最優先課題としているため、次々と出されるシステムの整備や調査・報告に対応する現場は疲弊し、「誰のための医療DXか」という悲鳴をよく耳にする。
今回の方向性では、①セキュリティ対策を向上しながら病院の費用逓減をはかり、経営資源を医療提供に振り向ける、②将来的に各病院が生成AI等の最新技術を活用しやすくし、医療従事者の負担軽減・質の高い医療を実現する─ をめざすとしており、医療機関にとって本来の医療DXというべきコンセプトであり期待が膨らむ。
2012年に本会が採用した電子カルテのクラウド化や仮想化技術、強固なセキュリティで電子カルテとインターネットの同一端末の使用、PHRを含めた医療情報連携等の方針が、明確な政策の方向性として提起されたことは感慨深い。
電子カルテの病院導入率は全国で50%を超えたが、ほとんどがオンプレ型システム、すなわち病院独自の電子カルテを院内サーバーで運用する閉鎖システムを採用。病院ごとにカスタマイズできる利点はあるが、システム更新時には、部門システムを含めて高額な投資が必要となる。
また、電子処方箋や生成AI等の最新技術・サービスを活用するにも、医療機関ごとにシステム構築・改修が必要で、IT利活用の制約は大きい。 国内電子カルテメーカーはこの閉鎖空間において成長してきたため機能性に優れるが、世界的な潮流からは後塵を拝しているのが現実である。
今回の方向性が実現すればクラウド上に展開される電子カルテを「所有する」から複数の病院で「共同利用する」形となり、システム更新時の莫大な費用を回避でき、個別のセキュリティ対策も軽減される。以上の方向性には期待感が膨らむが、実際には、中長期的に多くの課題がある。
25年度に電子カルテ標準仕様を作成し、30年には病院が利用できる環境整備を目標として掲げているため、クラウド型電子カルテ開発自体は急速に進むと思われるが、多数の部門システムがどこまで対応可能か……。その連携費用を含めたコストが本当に低減できるかは不透明である。
本会の部門システムでも、クラウド型に変更後に深刻な不具合が多発したり、契約後にクラウド型の実装を止め開発を見直すと一方的に宣告されたり、多額の費用をかけてのバージョンアップにもかかわらず機能や操作性が大幅に低下するなど、IT人材不足も大きな懸念事項である。
正しい方向性を具現化するための工程は、過去の事例に学び功を焦らず、「拙速巧遅に如かず」とならぬようにしなければならない。
■特別座談会 林 修一郎・厚生労働省保険局医療課長を迎えて
2026年度診療報酬改定を展望する
全国一律の診療報酬制度で地域の課題とどう向き合うか 先入観を持たずに議論を
2024年度診療報酬改定は、介護報酬、障害福祉サービス等報酬改定との同時改定、かつ団塊世代が75歳以上となる2025年を目前にしていたこともあり、今後の医療提供体制に向け てメッセージ性の強い内容となった。それを受けての2026年度診療報酬改定は、「新たな地域医療構想」で提起された2040年ごろの医療提供体制も踏まえつつ、未曾有の危機に直面 している病院経営にどう対応するかなど、注目すべき点の多い改定となる。そこで、厚生労働省保険局医療課の林修一郎課長を迎え、26年度改定で留意すべき点や制度のあり方、病院 が直面する課題への対応などについて意見交換した。
(以下、掲載省略)
~ご意見・ご感想をお寄せください~
より良い誌面づくりのためにも、会員をはじめ読者の皆様からのご意見・ご感想をお待ちしております。宛先は事務局までお願いします。 (Eメール:headoffice@ajhc.or.jp)